RPA「UiPath(ユーアイパス)」導入企業に聞く
RPAは導入しておしまいではない。何かあればRPAを活用できないかと考え続けることが重要。
HS情報システムズは、政府系金融機関への支援として、20年にわたり基幹業務システムの運用業務やヘルプデスク業務を担ってきました。それら業務の効率化のため、RPAソフトウェア「UiPath(ユーアイパス)」を導入しました。 その、UiPathの開発支援を担当したのが、バルキー・インフォ・テックです。CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)やCTI(コンピューターと電話の統合システム)を中心としたシステム開発に多くの実績があり、AI領域も含め幅広く事業を展開しています。 HS情報システムズの野村 章 氏(元代表取締役 CTO/現技術顧問)、熊木 勝則 氏(総合オン運用部)と、バルキー・インフォ・テックの西田 幸作 氏(執行役員)、野田 敦士 氏、そして、バーチャレクス・コンサルティングの祢津 邦賢も交えて、UiPathを活用したRPAの取り組みを伺いました。

手前より野村 章 氏(HS情報システムズ 元代表取締役 CTO/現技術顧問)、熊木 勝則 氏(HS情報システムズ 総合オン運用部)、西田 幸作 氏(バルキー・インフォ・テック 執行役員)、野田 敦士 氏(バルキー・インフォ・テック)、祢津 邦賢(バーチャレクス・コンサルティング)
RPAの導入検討を始めた課題意識
─RPAを導入するに至った背景を教えてください。

- 野村氏:
- 私は40年間、情報システムの開発・運用に関わってきました。 2011 年からHS情報システムズの代表を務めていましたが、2015 年からCTOとして直接現場を管轄するようになりました。そのとき驚いたのは運用業務のやり方が、私が現場に携わっていた20年前と何も変わっていないことでした。 昔ながらの手作業が多く、ルーティンワーク。人がやることですから、当然、ミスも発生していました。
- 熊木氏:
- 私が所属する総合オン運用部では、政府系金融機関の基幹業務システムの運用業務やヘルプデスク業務を担当しています。 その現場スタッフはみな、運用手順書に基づき、決められたオペレーション業務をそのまま継承していました。例えば紙やExcelデータ、PDFで送られてきた情報をタイピングやコピペして入力するといった具合です。紙だけでも100枚くらいあるのを何百回もやっていたんです。そのような業務がたくさんありました。
- 野村氏:
- つまり、決められたことを決められた通りにやることが運用業務だと長年考えられてきたわけです。
- 熊木氏:
- もちろん、そのなかでも改善に取り組んでいましたが、あまり効果が出ませんでした。むしろ、ミスをなくすために終わった作業をダブルチェックするなどしていたため、工数は増えていました。
─それでRPAを導入しよう、となったのですね。
- 野村氏:
- RPAを知ったのは1年ほど前のことでした。昔、EUC(エンドユーザーコンピューティング)という、情報システム部などではなく、システムを利用する業務部門が主体的にシステムの構築に携わる、という概念が流行した時期がありましたが、当時それを実現することは実際のところ難しく、実践することができませんでした。RPAを知り、やっとそれが実現できるのではと思いました。 システムは開発依頼するのではなく、実際の業務にあたっている自分たちで作る。そのようなツールはこれからの時代に最適だと思いました。RPAの普及は進んでいますし、スタンダードになると予感しました。
─1年前にRPAを知ったということですが、実際導入されるまでにはどんなポイントを検討されていたのでしょうか?

- 野村氏:
- RPA製品の検証に時間をかけておりました。動作の正確性は当然ながら、EUCが本当に実現可能か判断したかったのです。運用の現場にいるスタッフは自分たちでプログラミングをやったことはない、という人が多くいます。RPAには製品によって差があるものの扱うためにプログラミング的な要素が必要になります。そこに抵抗を感じる人がいるのではないかという危惧もあって、どの製品を導入したらよいのか、なかなか判断がつかなかったのです。 そのため、バルキー・インフォ・テックの西田さんに検証を依頼することにしました。西田さんは20年来の付き合いで、技術力が高く、私が信頼しているエンジニアのひとりです。
- 西田氏:
- 私が野村さんから「RPAを導入したい」という話を伺ったときは、「いくつか候補はある」という話でした。私もRPAに興味はあったものの、実際に触ったことはなかったので「一緒にやりましょう」となりました。 まず基準を設けて3つのRPA製品の評価をすることにしました。環境を用意し、バルキー・インフォ・テックで実際にパイロットを作って動かしてみました。その結果、UiPathが良いだろうと判断したのですが、それでも結論には至りませんでした。
─展示会でバーチャレクスを知ったとのことですが・・・。
- 野村氏:
- RPAの情報収集のために展示会に行きました。そこでたまたまバーチャレクスさんのブースに立ち寄りました。バーチャレクスさんは3つのRPAを扱っているというので、要件をお伝えして「一押しは?」と聞くと「UiPathです」との回答でした。それもあってUiPathに決めました(笑)。
─バーチャレクスのブースに立ち寄った理由は何だったのですか?
- 野村氏:
- RPA製品の開発側ではなく、コンサルティングをされているからです。客観的な話が聞けると思いました。私がRPAの情報を集めて検討するより、バーチャレクスさんに聞く方が効率的だと考えました。
数あるRPA製品の中でなぜUiPathか
─UiPathを評価したポイントはなんだったのでしょう?
- 西田氏:
- いくつかありますが、操作性に優れること、拡張性があることを高く評価しました。もちろん、3つのRPA製品を試してみてUiPathは動作中に起きる問題が一番少なかったということもあります。
- 野村氏:
- UiPathは、自動化できる範囲が圧倒的に広いんです。「何をやりたいのか」を登録していくツールだと思いました。できることが非常に多いのでツールの機能制約を念頭にやりたいことを考えるのではなく、まず、「"本来やりたい方法"で何をやりたいのか」を考え、それをUiPathで形にしていくプロセスが面白いと思いました。
- 熊木氏:
- 私はRPA製品の比較検討のところから関わっていましたが、UiPathはフローチャートを書いて、やりたいことを設計して行く作り方がとても良いと思いました。
─UiPathは海外製品です。その点での不安はありましたか?
- 野村氏:
- 検証しているとき、内部コードは日本語に対応していましたが、表面的な部分は英語でした。聞くと「近々、日本語版が出ます」とのことだったので、その点であまり不安はありませんでした。でも、なかなか出ませんでしたね(笑)。ちょうど導入したタイミングに日本語版がリリースされました。
- 西田氏:
- 社内トレーニングを開始したタイミングでウェビナー(UiPath Academy)も日本語化されたので、安心できました。
導入計画の策定方法
─どのような手順で導入は進められたのでしょう?

- 祢津:
- 展示会が5月にあり、9月にバルキー・インフォ・テックさんからバーチャレクスにご連絡をいただきました。導入をスタートしたのは10月からです。
- 西田氏:
- まず、業務一覧とそれぞれの業務の簡単な手順はすでに聞いていたので、そのなかからどれがRPA化に適しているのだろうと、優先順位をつけて洗い出しました。それをもとにwebからログを引っ張ってきてそれをExcelに流し込んで整形するというような、ロジックが単純なRPA化に適した業務でパイロット版のシナリオ(自動化する業務の設定)を9本作りました。また、効果測定も行い、何パーセント効率が向上するのかも数値化しました。業務の性質によっては効果が薄い、というものもありました。ここでRPA化に向いた業務の勘所が掴めたのも大きかったですね。
─その後はどのように進めたのでしょうか?
- 西田氏:
- 要望として現場スタッフが使えるものにしたい、ということがあったので、当初はパイロットをバルキー・インフォ・テックで開発し、現場のスタッフがそれを運用できるように教育も実施しました。いきなりRPAで業務を自動化しろと言われてもイメージがなければ戸惑ってしまいます。まずは、RPAがどうのように業務をこなすのか、人間との違いなどを認識してもらうところから始め、それから実際に自身で開発していただくといったように、RPAに関する作業を徐々に展開することで現場のスタッフに広めて行きました。
- 野村氏:
- 実際に、現場スタッフにデモンストレーションをやるわけです。普段自分たちがやっている業務だから内容はわかります。それが自動的に行われるので、みんなびっくりするんです(笑)。
─それは驚くでしょうね。
- 野村氏:
- なかには、「凄いですね」と言いながら、真顔になって、「自分たちは仕事がなくなるのでしょうか?」と聞いてきた人もいます。そんな人には「RPAがやってくれることでミスもなくなるし、今まで使っていた時間をもっと別のことに使えるようになります」と答えています。時間に余裕ができることはプラスになるはずです。
- 熊木氏:
- RPAを導入することで定量的な効果がわかりますが、それよりも現場の考え方が変わる、ということを肌で感じます。日々の業務をこなすことが自分のミッションだったけれど、その業務を代わりにやってくれるものが来たとき、我に立ち返るというか、「自分がやってきたことはなんだったんだろう」と考え、「新しいことにチャレンジしなければ/しよう」というマインドに変わって行くんです。ルーティンをこなしていた人のマインドセットが変わるのを見てRPAの凄さを実感しています。
教育体制
─現場の方への教育も実施されたのですね。
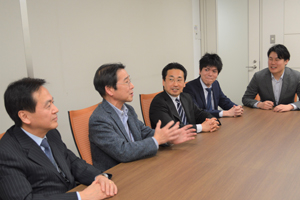
- 西田氏:
- 開発はもちろん、教育にもウエイトを置きました。セルフトレーニングをベースに、コンテンツをさまざま用意し、それを活用し、社内講習会や、バーチャレクスさんの講習会を受講することを繰り返していくスキームを作りました。
- 祢津:
- 我々はUiPathで開発される方がしっかりと自走できるようになることをメインとしてサポートさせていただきました。 バーチャレクスではUiPathでの開発の基礎をレクチャーするワークショップも実施しているので、そちらに毎月招待させていただきました。 UiPathはフレームワークを無視して作って行くと、それで稼働したとしても、後で保守が難しいものができてしまいます。最初の「どうやって作るものなのか」という基礎をしっかりと理解することが非常に大切になります。その基礎取得部分を支援させていただきました。それを理解していただけると、次の段階の「自分の業務をどうすればRPA化できるのか」を考え、応用することができるようになります。
- 野村氏:
- 3社で連携を取るため、毎月1回、定期的な会議を行い、開発メンバーから出てきた問題点を事前に共有し、それを元にレクチャーしていただく、という体制で情報交換を行いました。
- 祢津:
- HS情報システムズさんもバルキー・インフォ・テックさんもしっかりと計画を立てていらっしゃったので、我々はその計画通りにプロジェクトが進むように下支えをさせていただきました。RPA開発/運用体制の構築や立ち上げにおけるベストプラクティス、開発におけるティップスなど、バーチャレクスには蓄積された知見があるので、それを活用して支援させていただきました。
- 野村氏:
- 単純にライセンスを購入するだけのお付き合いではなく、バーチャレクスさんだとトータルでサポートしていただけたので、お願いしてよかったと思っています。
- 祢津:
- HS情報システムズさんは、しっかり現場を巻き込んで検証して、結果を出されています。他の企業のなかにはRPAを導入しても現場の協力を得られないことや、システム開発とRPAによる自動化の違いを正しく認識せず完璧なシステム化を求めてしまった結果、プロジェクトを凍結してしまい、進まない場合もあります。その点、HS情報システムズさんはしっかりとした計画と、その中でトライ&エラーを認めるスタンスによって成功されたのだと思います。
開発で苦労したポイント
─バルキー・インフォ・テックさんでの開発ではどのようなことに苦労がありましたか?

- 野田氏:
- UiPathでの開発は初めてでしたが、UiPathはオフィシャルのトレーニングや、インターネット上でのコミュニケーションも充実しているので、開発は比較的スムーズに進めることができました。また、UiPathのコアな技術的な部分で、どうしてもわからない、ということはバーチャレクスさんに教えていただけたので、そこにも問題はありませんでした。 ただ、私の場合は、UiPathの知識はあるけれど、業務知識が不足している、という点では苦戦しました。そのため、開発にあたっては、現場スタッフに詳細業務手順や判断ロジックを教えてもらいながら、どのような最終アウトプットを出したいがための手順・判断なのかをベースにUiPath用の手順・判断ロジックに作り替えるということを行いました。開発は常にトライ&エラーで進めました。
─現場からはRPA化の対象となる業務の候補はすぐに出ましたか?
- 西田氏:
- 出なかったですね。こちらから頼みに行かないとなかなか出ませんでした。
- 野村氏:
- マニュアル化されている業務もあれば、マニュアル化されていない業務もあります。また、マニュアル化されているものでも実際にはやり方が変わっている、ということもあります。そのため、実際に作業を行っているスタッフへのヒアリングは必須でした。
- 西田氏:
- 野田と共に現場でヒアリングしてくるのですが、当初はなかなか全ての情報が収集できませんでした。やはり最初はRPA化すると言っても現場ではRPA化して業務がどうなるのか、RPA化するためにはそもそも業務についてどこまで説明すればいいのか、イメージできていないんです。現場のスタッフが業務内容を伝えきれておらず、エラーが起きた時に、「実は・・・」という話が後からボロボロと出てきました。そのため、フィードバックを何度か繰り返さないとUiPathが最後まで動かない、ということもありました。
─徐々に現場スタッフの方にも開発を任せていったと伺っていますが、そちらはいかがでしたでしょうか?
- 熊木氏:
- 初期には野田さんに1日現場に張り付いてもらって開発したこともあります。現場での開発を始めてから、1か月すぎてもあまり進捗は芳しくありませんでした。そのため、「野村報告会」を開催することにしました。そこからは本格的に進むようになりました。
─「野村報告会」とは?
- 西田氏:
- CTOである野村さん主宰の報告会です。CTOに直接、自分で作ったシナリオをデモンストレーションしてプレゼンする、ということで現場スタッフはモチベーションが上がったようです。
- 野村氏:
- モチベーションというより、「発表しなければいけない」という緊張感ですね(笑)。 現場スタッフの多くは身体で覚えた作業手順を言葉にして人に説明するのはあまり得意ではありません。でも、発表会は人に説明する場なのでやるしかなかった。その意味で良かったのだと思います。
─野村さんも実際にUiPathでの開発をされたのでしょうか?

- 野村氏:
- 私もwebを自動的に検索して情報を編集するシナリオを作ってみました。するとUiPathと使用しているツールと相性が良くないものもありました。エラーのポップアップが出るのですが、なぜ、エラーになるのかがわからなかったり。それほど多くはなく、すぐに解決したのですが、どうすればよいかを考え、豊富な機能のどれを使えばいいのかを判断するのが少し難しかった、ということはありました。でも、作るのは楽しかったですね。
- 熊木氏:
- 私自身はほとんど触る時間がとれなくて。「ダメですよ」とよく怒られていました(笑)。でも、その分現場がやりやすいような環境づくりをしていました。結果的には導入した1部署で50ほど業務を洗い出し、25本くらいのシナリオを作りました。 RPAで自動化した主な業務は、業務・障害チケット集計、ワークフロー申請で利用する添付資料作成、顧客問い合わせ情報集計、各種ログ集計、週次・月次報告資料集計などがあり、自動化実績(2018/10~)は、業務数が25本。旧作業時間(年換算)2350時間だったのが、新作業時間(年換算)は700時間に短縮されました。削減時間(年換算) は1649時間。削減率は70.19%です。
─それは満足のいく結果でしょうか?
- 野村氏:
- 満足しています。一般的に数値が評価しやすいですが、私は品質向上の方が重要だと考えています。つまり、ミスが減ったことが大きなメリットです。特にミスを起こしてはいけない、という現場スタッフのストレスは軽減できたことは大きいと思っています。
今後の展開
─現場からの声にはどのようなものがありましたか?
- 野村氏:
- 2、3時間かかっていたことが5分で終わるのですから、「楽になった」という声がありました。 それに品質も間違いありませんから、不安もなくなります。間違ったらRPAのせいにできます(笑)。そもそも、そのシナリオを作ったのは誰なんだ?という話はありますが。前向きになっているのを感じます。
─前向きとは?
- 野村氏:
- 「この業務も自動化できるんじゃないの」とか「自分たちですぐに作ろう」という話が出るようになってきています。
─今後の展開を教えてください。
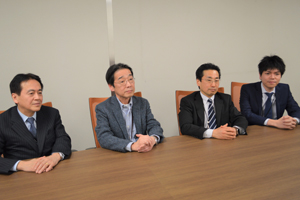
- 野村氏:
- 手順書がない作業がたくさんあります。次はその部分に取組みたいと思っています。 とにかく、RPAが導入されておしまいではなく、これからも何か問題があれば、RPAを活用できないか、と考えてみることを止めないで継続することが大切です。そこには終わりはありません。
- 西田氏:
- 立ち上がりがうまくいった今、より効率的に自動化を進めるためのスキームを作っています。UiPath含めRPAは今後も進化していくので、最新情報をキャッチアップしてHS情報システムズさんに続けてご支援したいと思っていますし、バーチャレクスさんにもご支援いただきたいと思っています。
- 野田氏:
- RPA活用をどのように拡大できるかを西田と一緒に検討していますので、今後も支援を続けて行きたいと考えています。また、このRPAの知見をもとに他の企業にも広げられればと思っています。
- 西田氏:
- RPAを活用しても最後は人間のチェックや判断が必要になると思いますが、RPAが苦手とする条件判断などは、一定AIで補完できると思います。RPAもAIなどと組み合わせることで効果が高まると思うので、そのような手段を提供していきたい。そんなお手伝いもしたいと考えています。ゆくゆくはRPAでAIのモデル更新サイクルの自動化なども行っていきたいと考えています。
- 祢津:
- 現状RPAは、業務の効率化、品質向上のためのツールと認識されることが多いですが、今後、多くの企業がRPAによって現状の業務効率化を達成した先には、もっと普遍的なツールとして認識されるようになると思います。RPA活用によって現場の余力が生まれるからというだけでなく、これから新たに取り組む業務もRPA活用を前提に設計することで、より少ないコストで実施できるのです。今まで工数見合いで断念していた業務にも取り組むことが可能になります。当たり前のことではありますが、この発想を経営層だけでなく、現場にも持ち続けていただけるように、様々なアプローチでご支援をしていきたいと思っています。


